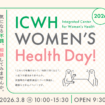#Me too運動のムーブメントの裏で、医療界のセクハラの実態を明らかに
本稿は、たちばな台クリニックの秋谷進医師による連載記事です。今回のテーマは「医療界のセクハラ」。かつて#Me too運動が世界的なムーブメントとなり、エンターテインメントやメディア業界のセクハラや性暴力の実態が次々に明らかにされましたが、実は、医療界のセクハラについても米国で明らかにされていました。その研究報告を解説します。
目次
#Me too運動の裏で問題視された医療業界のセクハラ
セクハラや性虐待、性的暴行の被害者たちが声を上げようと2006年に始まった「#Me too運動」。女性の権利を守るためのこの活動は、2017年に映画業界で大きなムーブメントを引き起こし、女性の権利を守る活動の象徴となりました。この#Me too運動で映画業界に蔓延るセクハラが明らかになったのですが、実は、映画業界だけでなく医療界のセクハラについても同時期に明らかにされています。今回は米国での医療界でのセクハラについて調査した研究を紹介します。米ミシガン大学神経科学研究所のElena Frank氏らによる、2024年3月「JAMA Health Forum」誌での報告です。(Elena Frank,Zhuo Zhao,Yu Fang,dt al. Trends in Sexual Harassment Prevalence and Recognition During Intern Year. JAMA health forum. 2024 Mar 01;5(3);e240139. pii: e240139.)
医療界におけるハラスメントを明らかに
研究背景:女性のインターン医師が受けるハラスメントの実態を明らかに
医師の初期研修(インターン)期間は医師としての専門的なスキルを習得する重要な時期です。しかしながら研修医はまだスキルが十分でない上に教育を受ける立場であることから、医師間の上下関係の問題にさらされやすく、職場でのハラスメントやストレスの影響を強く受ける時期でもあります。この研究は約4,000人の医師を対象に、性別に基づくハラスメントの経験やその認識の変化を調査したものです。特に女性医師の経験に焦点を当てて、医療現場における課題を明らかにすることを目的としています。
研究方法:インターンを終えた医師に調査
米国ミシガン大学のインターンプログラムである「Intern Health Study」に参加し、2017、2018、2023年にインターンを終えた医師から得たデータを分析する形で、研究が行われました。年齢の中央値は27歳で、女性の比率は52%でした。調査は、性別に関連した3種類のハラスメント「ジェンダーハラスメント」「望まない性的な注目」「性的強要」を評価する質問票「Sexual Experiences Questionnaire-Shortened/SEQ-S」を用いて行われました。
研究結果:5割以上が性別に関するハラスメントを経験
2023年のインターンでは、54.6%の男女が少なくとも1種類以上の性別に関するハラスメントを経験していることがわかりました。2017年では62.8%であったので、割合としては低下しているとも考えられるのですが、未だ半数以上のインターン医師が経験しているということがわかったのです。性別では、女性は2017年、2018年、2023年のいずれも70%以上でした(順に76.6%、76.8%、72.0%)。男性でも2023年の調査で50.9%と、半数以上が経験しているのです。
ハラスメント別にも見ていきましょう。性別に関連したハラスメントのうち「ジェンダーハラスメント(相手の性別に関連して不快感や屈辱を与える言動のこと。性的要求や身体的接触と伴わないもの。「女のくせに」「男のくせに」などの性別に関する差別的言動、女性だけに雑用を押し付けるなどの行為などが含まれる)」を経験した男女の割合は、2017年の61.0%から2023年は51.7%に減少していました。#Me too運動でも問題となった「性的強要」については、2017年は2.3%でしたが、2023年は5.5%と増加していました。
研究から得られた知見:医師の強い上下関係によるパワハラも改善を
近年、女性の権利意識の高まりもあり、性別で人を差別することが良くないことであるという認識自体は広まりつつあり、医療界でもジェンダーハラスメントは減少しつつあります。しかしながら、依然として半数以上の医師が「望まない性的な注目」「性的強要」といったセクハラを受けているという事実があり、引き続き、これらの問題に対する対応が求められます。また、性的強要については減少していない、ということも大きな懸念です。これはセクハラとしても問題ですが、年長の医師に若手の医師は逆らうことができない、という強い上下関係に関連したパワーハラスメント的な要素がいまだに拭いきれていないということの表れでもあると考えられます。医療界の人間関係の課題が修正されていき、ハラスメントに悩む医師を減らすことが喫緊の課題と言えるでしょう。
被害が起きやすい環境は男女比も関係、男性医師9割の「外科」と男女半々の「小児科」
時代も変われば常識も変わります。「常識だから…」と、何も考えずに当たり前だとそのまま受け入れてしまうのは危険です。1992年4月に全面勝訴という判決が下された日本初のセクハラ裁判の様子が、2022年NHKや2024年「ザ!世界仰天ニュース(日本テレビ)」で放送され、私も視聴したのですが、裁判当時は働く女性の地位が低く見られていて、それを当然だと社会も受け入れている様子が再現されていました。「そのような時代もあったなぁ」というのが私の感想でしたが、私の先輩である女性医師にとっては、あの報道ですごく気持ちが楽になったと言っていました。「これが正しい世の中の在り方なのだ。私は間違っていなかったのだ」と。彼女曰く医療現場でもセクハラはあったそうですが、それよりもジェンダーハラスメントがひどく、仕事で失敗すると「やっぱり女だから」と言われ、成功すると「女のクセに」と陰口だけでなく面と向かって言われたこともあったそうです。私が所属する小児科は女性医師が50%で女性も多いので、女性蔑視などはなく男女公平の配慮がされている印象を日頃から感じていますが、彼女の所属する外科は男性が90%を超えるため配慮が欠けており、男女公平からはほど遠い世界だったようです。
今回紹介した論文では、女性にセクハラ被害が多い理由までは議論がされていません。ちなみにこれまでの報告では、日本も米国も管理職の女性は非管理職の女性に比べ、セクハラ被害を告発する傾向があることがわかっています。発言力のある立場にいるから告発が可能なのか、その理由は未だ明らかにされていません。本来、管理職の女性は護身のため、セクハラ告発を回避する傾向があるとも考えられているので、この2つの見方には矛盾もあり、未だにそんな議論がされているほど、セクハラに関して明確になっていないことは多いのです。
この論文では、医療界では依然としてセクハラが存在することがわかりました。「#Me too運動」や「#私たちは黙らない」と言った言葉を『男女間の個人的対立』としてとらえるのではなく、社会の在り方を変えるために考えなければならない問題だと考えます。
【執筆】秋谷進
小児科医・児童精神科医・救命救急士。たちばな台クリニック小児科勤務。1973年東京都足立区生まれ、神奈川県横浜市育ち。1992年、桐蔭学園高等学校卒業。1999年、金沢医科大学卒。金沢医科大学研修医、国立小児病院小児神経科、獨協医科大学越谷病院小児科、児玉中央クリニック児童精神科、三愛会総合病院小児科、東京西徳洲会病院小児医療センターを経て現職。

【編集部おすすめ記事】
■世界で解明が進む性差「ジェンダーペインギャップ」の研究で女性特有の痛みが明らかに
■医療現場でも軽視される痛みの性差、「ジェンダーペインギャップ」とは?
■女性の健康・医療にまつわる世界の研究報告トップ5、現役医師が解説するビジネスの種
■女性看護師の高い自殺率、実態把握のため米国で大規模調査 約16万人の自殺データ解析
■女性における「カフェイン摂取」と「認知症・認知障害」の関連、5,060人データ