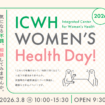実は悪いことばかりではない「無給労働」、男女ともにメンタルヘルスへの良い影響が明らかに
本稿は、たちばな台クリニックの秋谷進医師による連載記事です。今回のテーマは「無休労働とメンタルヘルス」。働く女性のメンタルヘルスというと、職場や仕事に起因するストレスが着目されがちですが、家庭内で行われる無給労働からくるストレスにも着目すると、新たな気づきや課題と共に、良い側面も見えてきます。女性の社会進出により、「有給労働」と「無給労働」のダブルワークをする女性が増える中、無給労働とメンタルヘルスの関連に着目した研究報告を解説します。性差分析による興味深い男女の違いも、要注目です。
目次
無給労働、女性6時間・男性2時間
家事や育児、介護など家の中の仕事で給与が発生しない無給労働は多くの人にとって日常的でありながら、負担もかかり、心身にさまざまな影響を与えます。近年は女性の社会進出が進みつつありますが、まだまだ女性の方が無給労働を多く担っている現状があり、無給労働の実態を明らかにすることは、私たちの生きる社会にとって大きな課題となっています。世界のすべての地域の女性は、1日平均3〜6時間を無給労働に費やし、男性は0.5〜2時間を費やしています。今回は無給労働がメンタルヘルスに対して与える影響についての研究を紹介します。オーストラリア・University of MelbourneのJennifer Ervin氏らが、家事、育児や介護などの無給労働とメンタルヘルスの関連を検証する研究を実施し、Lancet Public Healthに2023年4月に報告しました(Jennifer Ervin,Yamna Taouk,Belinda Hewitt,et al.The association between unpaid labour and mental health in working-age adults in Australia from 2002 to 2020: a longitudinal population-based cohort study.Lancet Public Health. 2023 Apr;8(4):e276-e285. doi: 10.1016/S2468-2667(23)00030-0.)。
無給労働がメンタルヘルスに与える影響
研究背景:見過ごされてきた無給労働とメンタルヘルス、性差にも着目
家事や育児、介護といったお金にはならない仕事=無給労働は、多くの人が日常的に担っています。特に女性が担うことが多く、「家庭での無給労働」と「会社などでの有給労働」とのダブルワークになることも多くなっています。そのため、負担が大きくなり心の健康への影響が懸念されています。これまで有給労働に関する研究は行われてきたものの、家庭での無給労働に目を向けた研究はほとんどなく、男女の違いをまとめた研究もほとんどありませんでした。この研究では以下の2つを目的として行われました。
1.家事、育児、介護などの無給労働がどのようにメンタルヘルスに影響するのかについて明らかにする。
2.男女で無給労働とメンタルヘルスの関係に違いがあるかについて明らかにする。
研究方法:家計所得と労働力に関する動態調査を分析
2002年から2020年までの19年間にわたって、オーストラリアの25〜64歳の国民およそ37,000人を対象とした家計所得と労働力に関する動態調査のコホート研究を行いました。欠損データがあるなど問題のあるデータを除いて、21,000人が分析の対象となりました。調査は次の4種類の無給労働について行われました。
- 家事:掃除や洗濯、料理など
- 育児:子どもの世話
- 介護:高齢者や障がい者のケア
- 屋外作業:ガーデニング、外構の修理など
これらの無給労働を行った週ごとの平均時間を調査しました。メンタルヘルスの尺度としては、MHI-5という質問表を用いた調査を毎年実施し、その得点で評価をしました(0〜100スケール:低いほど精神状態が悪い)。
研究結果:女性は男性より無給労働が週16時間多く、男性よりもメンタルスコアも低い
女性は男性よりも総無給労働時間がかなり長く、その差は16時間/週でした(女性38.08時間/週、男性21.89時間/週)。家事と育児は無給労働時間の大部分を占め、女性はいずれの領域でも男性の2倍の時間を費やしていました(家事は女性20.86時間/週、男性10.05時間/週、育児は女性12.48時間/週、男性5.97時間/週)。4項目における平均メンタルヘルススコアは、女性の方が男性よりも低かった(女性72.42、男性74.42)。それぞれの作業ごとに以下のような傾向が見られました。
【家事】
男女ともに、家事の量が多くなるとメンタルヘルスに悪影響がありました。
【介護】
女性では介護時間が増加することでメンタルヘルスに悪影響がありました。男性には明確な影響は認められませんでした。
【育児】
女性では育児の時間が増えるとむしろメンタルヘルスが改善するという結果となりました。男性には明確な関連は見られませんでした。
【屋外作業】
男性は屋外作業を増やすと、メンタルヘルスはむしろ良くなる傾向が見られました。女性にはそのような目立った関連はありませんでした。
無給労働の多くの時間を占める上記4項目を全体で見ると、男女共にメンタルヘルスとの関連はありませんでした。これは無給労働の一部領域はメンタルヘルスにマイナスの影響を及ぼしたとしても、他領域がプラスの影響を与えたことを示唆することに他なりません。
研究で得られた知見:無給労働に関するジェンダー格差
今回の研究で、単に無給労働をすればするほど悪い影響があるというわけではなく、男女それぞれにメンタルヘルスに良い影響を与える無給労働が存在することがわかりました。女性と男性の両方にとってメンタルヘルスにマイナスの影響がある唯一の無給労働は「家事」でした。女性は「家事」「介護」の負担が重なるとメンタルヘルスの悪化をもたらす一方で、「育児」はプラスの影響を及ぼします。男性では屋外作業がプラスの影響をもたらします。無給労働の影響には性差があり、本研究により、幸福をもたらすための仕組みについて知識と理解が深まったと言えるのではないでしょうか。
ただ、近年女性の社会進出が進められているにもかかわらず、無給労働に対してジェンダー格差がいまだに大きくあることも、本研究で明らかになりました。そして、女性にとって有給労働と無給労働のダブルワーク状態が持続すると、肉体的にも負担が大きく、心理的なストレスや疲労感などを引き起こす危険性があることも示唆されました。加えて今後の課題としては、女性は無給労働時間があることによって、有給労働時間を失っている可能性についての検討も必要です。
子どものお迎えで痛感、「家事育児は女性がするもの」
今回は無給労働とメンタルヘルスの関係についての論文を紹介しました。「家事育児は女性がするもの」という考えは未だに根強いと、私自身も実生活で感じたことがあります。私の妻が2人目の子を出産する前は、娘の幼稚園の送迎は私がしていました。そのため、職場には事前に時短勤務を申し出ていました。時短と言っても、勤務時間通りに退勤するというものでした。小児科という職場は子育てに寛容なので、退勤時間近くになると周りが気を遣ってくれ、残業にならないように配慮してくれていました。ところが、退勤間近に救急搬送されてきた患者さんを診療していた非常勤女性医師が突然、「秋谷先生、私は子どものお迎えがありますので、帰らせていただきます」と、一言だけ残して帰られたことがありました。「私も子どものお迎えが…」と言いかけたところで、彼女に「秋谷先生は、何か家に帰ってやることあるんですか?」と言い切られてしまいました。結局何も言えず、他のスタッフもそれぞれ仕事を抱えていたので、私が引き継いで診療することになり、勤務時間がかなり超過してしまいました。お迎えの時間が気になり、気が気でなかったのですが、結局は幼稚園から苦情の電話を受けてしまいました。
帰り道、頑張って仕事をしていたのに、なぜこのような思いをしなければならないか悲しくなりました。私に任された家事育児は子どもの送り迎えくらいでしたが、家事は本当に多岐にわたり、料理一つとっても、献立を考えて買い物して調理して後片付けもあります。世の中の働くお母さんも、きっと我慢しなければならない思いをしているのだろうと、そんなことを考えていると、我が子が心配そうに私の顔を覗き込んできました。それを見て、私は「子育てをやりたくてしているのだから、仕方がない。子どものために頑張るのだ」と、気持ちを切り替えることができました。親である私を頼っている子どもに私は支えられているのだと、強い心を取り戻したのです。
今回紹介した研究では、女性は男性より無給労働が週16時間多く、男性よりもメンタルスコアも低いことが明らかになりました。「無給労働は悪影響」と一括りにできず、「家事・介護」「育児・屋外作業」でメンタルヘルスに与える影響は異なるということがわかりました。男女の特性を理解して分担したり、男女のどちらかに負担が集中しないように家事・介護の負担軽減、男性の育児参加推進、休暇制度や社会保障の充実などが、社会の大きな課題と言えそうです。
【執筆】秋谷進
小児科医・児童精神科医・救命救急士。たちばな台クリニック小児科勤務。1973年東京都足立区生まれ、神奈川県横浜市育ち。1992年、桐蔭学園高等学校卒業。1999年、金沢医科大学卒。金沢医科大学研修医、国立小児病院小児神経科、獨協医科大学越谷病院小児科、児玉中央クリニック児童精神科、三愛会総合病院小児科、東京西徳洲会病院小児医療センターを経て現職。過去の記事一覧はこちら。

【編集部おすすめ記事】
■女性看護師の高い自殺率、実態把握のため米国で大規模調査 約16万人の自殺データ解析
■これまで研究されてこなかった「女性のうつ」と「日本食」の関連を明らかに
■女性における「カフェイン摂取」と「認知症・認知障害」の関連、5,060人データ
■子どもの時の肥満がPMSの早期発症やPMDDのリスクに 女性6,524人を調査
■世界で解明が進む性差「ジェンダーペインギャップ」の研究で女性特有の痛みが明らかに