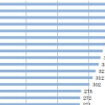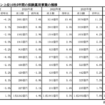働く女性の「過剰適応」がメンタルヘルス不調へ発展、事例から学ぶ健康経営・女性活躍に必要な予防策とは?
本稿は、企業の健康経営と労働安全衛生を20年以上にわたり支援する、さんぎょうい株式会社による連載記事です。前回の「社内で停滞する女性の健康推進の打開策」に続き、実際の支援現場で見てきた事例をもとに解決策を示していきます。今回のテーマは「メンタル不調」。働く女性に見られがちな「過剰適応」の視点から、予防方法を解説します。
目次
女性のキャリア形成とメンタルヘルス
女性が活躍できる環境を整えてリーダーや管理職へと積極的に登用することは、組織の多様性を高める上で重要な施策です。しかし、女性特有の健康課題やライフイベントなどへの理解が不足したまま、男性のキャリア形成と同一に進めると、その意欲や能力を十分に引き出すことは難しくなります。何故なら、例えば、妊娠・出産・育児といったライフイベントは、キャリアの中断や働き方の変化を余儀なくする上に、月経に伴う体調不良など、男性には理解されていない健康課題も存在するからです。これらの性差に起因するさまざまな差異を理解しないまま、これまで通りの画一的なキャリアパスやキャリア支援を押し進めれば、女性の負担は物理的にも精神的にも増して、キャリアアップを諦めるだけでなく、仕事の継続さえも危ぶまれることになります。
女性は、男性と同じようにキャリアを歩むことに困難を感じることが多くあります。その要因は多岐にわたり、根強い性別役割分担意識、育児・家事との両立の難しさ、ロールモデルの不足、評価や機会におけるジェンダーバイアス、ハラスメントや差別、ネットワークの構築の難しさなどが挙げられます。そして、女性はホルモンの影響を受けやすいという身体的な特徴に加え、社会的な環境や慣習によって、男性よりもストレスを感じやすい傾向があることも見逃せません。実際に、働く女性のメンタルヘルス不調は、一般的に男性よりも女性に多く見られます。
本記事では、女性のキャリア形成期におけるメンタルヘルスに焦点をあて、働く女性が抱えやすいストレスとその要因、そして企業の取り組みについて掘り下げていきます。
女性のキャリア形成を阻むメンタルヘルス不調、ある女性の事例
それでは、実際に働く女性がキャリアとライフイベント、そして職場環境との間でどのような葛藤を抱えているのか、具体的な事例を、当社の臨床心理士が実際に相談を受けた事例を通して見ていきましょう。次にご紹介するXさんのケースは、多くの働く女性が直面する可能性のある課題を示唆しています。
Xさんは大学卒業後、希望の業界で営業職に就き、積極的なアプローチで評価を得ていた。31歳で企画部門に異動し、結婚も決まり充実した日々を過ごしていた。しかし、企画部門の業務スタイルに戸惑いを感じ、発言の機会も限られ、もどかしさを覚えるようになってきた。会議では「女性としての意見」を求められることが増え、当初は喜んでいたが、「女性としてどう思うか」と問われるなど、性別を前提とした評価に違和感を抱くようになった。積極的に意見を述べるも、周囲の反応に難しさを感じることが増えていった。
その後、子どもを持つことを決め無事妊娠し、職場の制度を活用し産休・育休を経て復帰した。早く業務にコミットしたいと考えていたが、周囲の発言には「育児を優先すべき」という前提があり、希望していたプロジェクトにも参加できなかった。キャリアへの不安と悔しさを感じながら、仕事と育児の両立を目指したが、夫からはペースを落とすよう心配され、上司からは周囲の配慮に感謝するよう促された。次第に心身の不調に悩まされ、家族からも仕事をセーブするよう勧められる。Xさんは、自身のキャリアと家庭のバランスに深く悩むようになった。そして、不眠や意欲の低下といった症状が現れ始めた。
事例から見る3つのイシュー
この事例で、Xさんがやがて不眠や意欲の低下などの症状を覚えるようになった要因を整理します。大小さまざまな要因がありますが、本稿のテーマに添う3点に絞って解説します。
■アンコンシャスバイアスのミルフィーユ
会議の場で「女性として」という枕詞をつけて発言することや、育休復帰後の業務調整は、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)が女性のキャリア形成に影響を与える典型的な例です。意見を述べる場面で「女性としてどう思うか」と問われることで、性別に焦点が当たり、本人の能力や専門性への期待が十分に反映されていないと感じられます。このようなバイアスが積み重なることで、女性のストレスは増大してしまいます。
■キャリア選択に影響する外的要因
「母親だから」という理由での業務負担の調整は、根強い性別役割意識の表れと言えます。業務負担の調整は、女性のワークライフバランスを守るための配慮として機能する場合もありますが、本人の意欲に関係なく役割を固定化すると、女性がキャリア形成を進めることに困難を覚えるようになります。
■女性に多い「過剰適応」も要因に
Xさんが仕事の成果と育児の両立を必死にこなそうとした結果、ストレスが増大し体調を崩してしまった背景には、女性に多い「過剰適応」が潜んでいる可能性があります。社会的な期待や役割意識から、「完璧な女性」「良い母親」であろうと無理をしてしまう傾向が、女性には見られることがあります。周囲からの配慮に応えようと頑張りすぎるあまり、自身の心身の限界を超えてしまうケースも少なくありません。
女性従業員のメンタルヘルス不調に有効、4つの予防策
Xさんのように、若いうちに高いパフォーマンスを発揮していた女性が、仕事やライフイベントの転換期を境に葛藤を多く抱えるようになり、メンタルヘルスを害する事例は珍しくありません。では、このようなかたちで女性従業員がメンタルヘルス不調に陥り、さらに高じて退職してしまうことを予防するために、企業は何をするべきでしょうか。
アンコンシャスバイアスを学ぶ
アンコンシャスバイアス研修は、最近導入する企業が増えています。この研修は、女性活躍の障害を取り除くだけでなく、偏見や固定観念を是正し、意思決定の質向上やイノベーション促進にも役立ちます。
メンタルヘルスを学ぶ
アンコンシャスバイアス研修と同様に、組織全体でメンタルヘルスへの理解を深めることが不可欠です。男女問わずメンタルヘルスについて学ぶ機会を設けることで、職場内の意識を変え、互いに支え合える文化を共に築けるようになります。特に、性別によってメンタルヘルスのリスク要因が異なることや、多くの男性管理職が経験しない女性特有のメンタルヘルス課題については、男性の理解が欠かせません。ホルモンバランスや社会的期待から生じるストレスについて知ることで、男性もより適切な配慮や支援が可能となります。
女性向けのマネジメントを学ぶ
リーダーや管理職の育成を目的とした女性向けのマネジメント研修も有効です。リーダーとしてのスキル向上に加え、ロールモデルの不足やワークライフバランスといった女性が直面しやすいキャリア課題に対する具体的な対策を学ぶ場を設けることで、リーダーや管理職としてキャリアアップを図ることへの確かな自信を育むことができます。
専門家によるカウンセリング・コンサルティングを受ける
さらに、臨床心理士などによるカウンセリングやキャリアコンサルタントのコンサルティングを活用すると、女性がキャリア形成のうえで抱える悩みや不安を専門家が解消し、具体的な行動を後押しできます。女性社員が抱える、「今の仕事への疑問」「将来のキャリアパスが見えない」「ワークライフバランスの課題」などの多岐にわたる悩みについて、臨床心理士は心理的側面から心の健康をサポートし、キャリアコンサルタントは実践的な目標設定やスキル開発を支援します。前段で指摘した、女性に多い過剰適応を軽減することにも役立ちます。
まとめ
女性のキャリア形成とメンタルヘルスの課題は、個人の努力だけでは解決できない複雑な要素を含んでいます。本稿で触れたXさんの事例のような女性が直面する固有の課題を深く理解し、アンコンシャスバイアス研修、メンタルヘルス研修、女性向けマネジメント研修、そして専門家によるカウンセリングやコンサルティングといった多角的な施策を講じることで、企業は女性従業員の心身の健康を守り、長期的なキャリア形成を支援できます。特に、専門家によるカウンセリングやコンサルティングは、女性に多い過剰適応の傾向を軽減し、自身の心身の限界を超えて無理をしてしまうことを防ぐことにも役立つでしょう。
また、今回のコラムでは触れませんでしたが、メンタルヘルス以外の女性特有の健康課題についても、すべての働く人が理解することも大切です。これらの取り組みが、個々の女性が抱える葛藤を解消することに役立ち、女性が安心して働き続けることのできる環境が生まれます。そして、より多様で活力ある組織文化を醸成するだけでなく、最終的には企業全体の成長と持続的な発展に寄与するでしょう。
(文:阿曽泰三)
【提供元】 さんぎょうい株式会社
産業医、臨床心理士、保健師、看護師、管理栄養士、理学療法士、社会保険労務士など、医療・健康のエキスパートによるチーム体制で、企業の労働安全衛生と健康経営を20年以上にわたり支援しています。本連載では、当社がこれまで蓄積してきた知見を元に、「健康経営」「両立支援」「女性活躍」に関する実践的な情報を、実際に企業支援の現場で見てきた多様な実例と解決策を取り上げながら紹介していきます。本稿でご紹介した「女性のメンタルヘルス不調」に関連する管理職研修や職員研修の詳細は、こちら。産業医の紹介や、健康経営の認定サポート、女性の健康経営も併せて提供しています。
【編集部おすすめ記事】
■女性活躍から10年、法令対応は義務から戦略へ イノベーションを生む土台の作り方
■制度は完璧なのになぜ浸透しない? 健康経営を阻む「見えない空気」の正体とは
■女性は仕事を諦めるべきなのか? 健康問題とライフイベントを突破したRさんの話
■社内で停滞する女性の健康推進、どう突破する? ケーススタディに学ぶリアルな打開策
■働く女性の「健康」と「活躍」、加速する一体型支援の動向がわかる記事4選