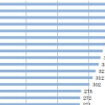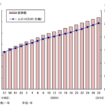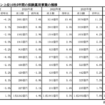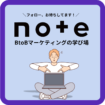社内で停滞する女性の健康推進、どう突破する? ケーススタディに学ぶリアルな打開策 健康経営支援の現場から
本稿は、企業の健康経営と労働安全衛生を20年以上にわたり支援する、さんぎょうい株式会社(東京都・新宿)による連載記事です。近年、女性従業員の健康づくりに取り組む企業が増えていますが、実際は「なかなか浸透しない」という声も多く聞かれます。どうしたら突破できるのか?その鍵は、「ヘルスリテラシー教育をキャリア形成に位置づけること」や「戦略的な土壌づくり」にあるようです。企業支援で実際にあった事例を取り上げながら、具体的な解決策を示します。
目次
「フェムテック」と「女性の健康経営」に共通するガラスの天井
近年、女性の健康課題への関心が高まる中、フェムテック市場は急速に拡大しています。また、健康経営においては、女性従業員のプレゼンティーズム改善の手段としてフェムテック製品が注目され、利用が進んでいます。
その一方で、フェムテック市場は成長しているものの、競争激化やニーズのミスマッチにより撤退する企業も出ています。日本の市場は特に成長が緩やかで、認知度の低さや議論不足、法規制の遅れなどが原因とされています。同様に、健康経営では女性の健康課題への取り組みが重要視され、フェムテック製品を活用する企業が増えている一方で、利用者が一部に留まり、期待された効果が得られていないという担当者の悩みを聞きます。その背景には、女性特有の健康課題に対する認識不足、製品利用への抵抗感やプライバシーへの懸念、周知不足などがあると考えられています。
そして、フェムテック市場の成長と女性の健康経営の両分野に共通する課題は、そもそも女性特有の健康課題に関するリテラシーの低さです。一見すると、冒頭で触れた女性の健康課題への関心が高まっているという認識と矛盾しているように思われるかもしれません。しかし、社会全体で見れば、女性特有の健康課題への関心は依然として十分ではありません。このような状況が「ガラスの天井」として立ちはだかり、結果としてフェムテックや女性の健康経営のブレイクスルーを妨げているのです。
女性特有の健康課題のリテラシーの低さが、学習意欲の低さに影響?
自発的なヘルスリテラシーの向上は期待できない
女性特有の健康課題に関するリテラシーの低さは、学校教育における性教育の不足が深く関わっています。日本では性について学ぶことがタブー視されがちで、女性自身が体の変化や健康について正しい知識を得る機会が限られていました。そのため、女性の間でも、女性特有の健康課題についてオープンに話すことをためらう風潮を生み出していると考えられます。
加えて、そもそも日本人は、諸外国に比べてヘルスリテラシーがかなり低いことが分かっています。その原因はいくつかありますが、一つには、日本は健康保険制度が充実していることにあります。健康保険で医療を安価に受けられることが、「病気になったら病院や診療所に行けばいい」という意識を生み、それが普段から健康や医療について学ぼうという意欲を阻害している、とも考えられています。
「低リテラシー」が「低学習」を生む、負のスパイラル
当社が企業の健康経営を支援するにあたって実際にあった、健康に関する学習意欲の低さを示す企業での事例をご紹介しましょう。その企業は、平均年齢が30歳前後の若い女性従業員が多く活躍している企業でした。そこで人事担当者が、「女性従業員のヘルスリテラシーを向上させたい」という想いから、女性特有の健康課題に関する研修を実施したいと経営者に上申しました。ところが経営者(男性)が研修の必要性を判断しかねたため、社員にこの研修を受講したいかを尋ねるアンケートを実施しました。結果は、「健康よりも業務上のスキル向上に役立つ研修を受けたい」という回答がほとんどでした。
この結果は容易に想像できるものでした。なぜなら、若い世代は病気を患う割合が低いので、総じて具体的な健康リスクを意識しにくい傾向があるからです。それに、生理不調を感じる若い女性はとても多いものの、「生理は病気ではない」という認識から、生理不調を健康課題とは捉えにくい傾向があります。ですから女性従業員からしたら、「せっかく研修を受けるなら、キャリア形成に直接的に繋がるスキル学習をしたい」と思うのは自然なことです。
組織のヘルスリテラシーを向上する方法と効果
ヘルスリテラシー向上のプロアクティブアクション
上述の事例のように、健康について積極的に学ぶ意欲が低いなかで組織や集団のヘルスリテラシーを向上させるには、どうしたら良いのでしょう?それは、学ぶ意識の土壌づくりから始めることです。具体的には、まず、ヘルスリテラシー教育をなぜ行うのか、その意義を次の通り明確にします。
- ヘルスリテラシーは、従業員のキャリア形成に必須の知識・スキルである。
- 組織全体のヘルスリテラシーの向上は、組織の活性化を図り、生産性を高める。
その上で、ヘルスリテラシーの重要性が分かる研修を、受講を必須として実施します。従業員が研修でヘルスリテラシーの重要性を理解することで、その後の自発的な学習も期待できるようになります。女性特有の健康課題研修の効果について言えば、研修を受講することで、女性従業員はセルフケア・セルフコントロールへの理解と意識が向上し、プレゼンティーズムやアブセンティーズムが改善します。フェムテック製品の利用も向上すると期待されます。また、男性従業員は、自分とは異なる身体の特徴と健康課題を理解することで、その知識を適切なコミュニケーションと配慮に活かせるようになります。このことは、アンコンシャスバイアスの改善にも役立つでしょう。
土壌づくりのはじめは、管理職から
特に女性特有の健康課題研修は、管理職から実施すると効果的です。なぜなら、大多数の企業では管理職の多数が男性で占められているからです。総じて男性は女性特有の健康課題について理解が乏しいので、その状態では、女性従業員が研修で学んだ知識を十分に生かすことができない可能性が高いのです。ちなみに、実は女性管理職であっても、女性特有の健康課題の理解が十分でない人が多いこともわかっています。
そこで、職場の組織風土に高い影響力を持っている管理職から研修を実施することで、職場の性差理解の土壌が改善します。土壌が整うことで、その後の研修対象者の拡大や継続的な取り組みが容易になり、やがて女性特有の健康課題のリテラシーが組織に浸透します。
このような研修を受講した多くの男性管理職から、「もっと早く知っておくべきだった」「研修を受けたことを部下に話したい」「全社員が受講すべき」という感想を聞きました。女性管理職も大多数が、「学べて良かった」「更年期や生理のつらさに、こんなに個人差があるとは思わなかった」と回答しています。これらの声から、女性特有の健康課題研修は、マネジメントスキルとしても歓迎されていることが分かります。
まとめ
- フェムテック市場の成長と、健康経営における女性の健康課題への取り組みに共通する課題として、女性特有の健康課題に関するリテラシーの低さが挙げられる
- リテラシー不足の背景には、学校教育における性教育の不足や、日本人のヘルスリテラシーの低さがあり、特に若い世代では健康よりもキャリア形成を優先する傾向がみられ、企業が研修を実施しても関心が低いという現状も
- 組織のヘルスリテラシー向上は、キャリア形成の土台となり、組織の活性化や生産性向上に不可欠。従業員教育の一環として研修を実施し、ヘルスリテラシーの重要性を理解してもらうことが重要
- 女性特有の健康課題研修は、管理職から始めると効果的。管理職の理解が深まることで、職場全体の意識改革につながり、研修の効果を高められる
今回のコラムが、女性の健康課題のリテラシー向上につながり、女性の健康経営推進とフェムテック製品の利用促進の一助となれば幸いです。
(文:阿曽泰三)
【提供元】 さんぎょうい株式会社
産業医、臨床心理士、保健師、看護師、管理栄養士、理学療法士、社会保険労務士など、医療・健康のエキスパートによるチーム体制で、企業の労働安全衛生と健康経営を20年以上にわたり支援しています。本連載では、当社がこれまで蓄積してきた知見を元に、「女性活躍」「健康経営」「両立支援」に関する実践的な情報を、実際に企業支援の現場で見てきた多様な実例と解決策を取り上げながら紹介していきます。本稿でご紹介した「女性の健康経営」に関連する管理職研修や職員研修の詳細は、こちら。産業医の紹介や、健康経営の認定サポート、メンタルヘルスサポートも併せて提供しています。
【編集部おすすめ記事】
■女性活躍から10年、法令対応は義務から戦略へ イノベーションを生む土台の作り方
■制度は完璧なのになぜ浸透しない? 健康経営を阻む「見えない空気」の正体とは
■女性は仕事を諦めるべきなのか? 健康問題とライフイベントを突破したRさんの話
■働く女性「過剰適応」がメンタルヘルス不調へ発展、健康経営・女性活躍に必要な予防策
■働く女性の「健康」と「活躍」、加速する一体型支援の動向がわかる記事4選