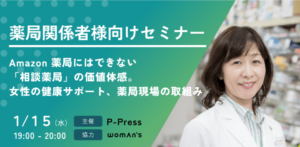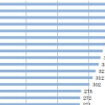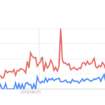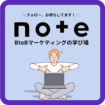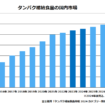Amazon薬局にはない価値とは?「女性の健康支援」に取り組む薬局の事例から議論
処方薬のオンライン販売サービス「Amazonファーマシー」の登場で中小薬局の淘汰が進むとみられる中、生き残りを賭け、”リアルならでは”の強みを活かした健康支援に取り組む動きが出てきている。Amazonファーマシーにはできない薬局の価値とは何なのかーー?今月15日、各地域の薬局・薬剤師がオンラインで集い、「Amazon薬局にはできない相談薬局の価値体感。〜女性の健康支援、薬局現場の取組み」をテーマに議論が行われた(主催:P-Press、協力:ウーマンズ)。
主催は、業界新聞紙『調剤薬局ジャーナル』の元編集長が3年前に立ち上げた、薬局業界のオンラインメディア『P-Press』。創刊編集長の石川良昭氏は、薬局への取材活動を長年続けてきた中で「薬局だからこそできる健康支援がある」とし、その議論の場として、薬局・薬剤師が集まるオンラインイベントの開催を企画した。議論を通じて目指すのは、地域の薬局・薬剤師が患者とオンライン上でつながれる場づくりで、健康相談ができる”オンラインコミュニティ薬局”の構想を掲げる。オンラインコミュニティ薬局での交流を重ねることで、患者が近所の薬局を「かかりつけ薬局」と認識し、処方薬の受け取りのみならず健康相談もできる場所として、患者が気軽に薬局に出向く流れを生み出そうとしている。
そんな薬局のあり方を模索しようと、イベントには各地の薬局・薬剤師が集まった。基調講演は、大岡山北口薬局(東京・大田)の管理薬剤師で、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門薬剤師の杉本園子氏。自身が勤める薬局では患者の来局機会を増やそうと、骨密度測定会の開催などリアルの場でしかできない健康づくりの場を定期的に提供している。目的は来局増だけではない。健康にまつわる知識を伝えたり近隣のクリニックと連携するなどして、患者が適切な医療の選択や適切な方法で健康を維持・増進できるよう、患者のヘルスリテラシー向上に努めている。
近年力を入れるのは、女性の健康支援。生理・妊娠・出産・更年期・高齢期の健康リスクなど、女性は生涯にわたり女性ホルモンに振り回されるものの、自分のライフステージと健康の関わりを理解していない女性が多いことを痛感してきたからだという。女性ホルモンに特に左右されやすい10代〜中年期、女性ホルモン減少による影響を受ける高齢期まで、幅広い女性特有の健康問題に対応できるよう、丁寧なコミュニケーションと啓発を重視しながら、女性が持つべき健康知識や、日常生活でできる解決方法を局内でアドバイスしている。
こういった日々の積み重ねにより、同薬局は患者の悩みに寄り添う存在として地域で認識されるように。ある女性は「クリニックには行きたくない。薬局で相談したい」と、医療機関での受診前に来局した。「私の妻の健康状態を見てほしい」という男性や、3世帯で来局する女性患者も増えてきたという。
クリニック受診に抵抗がある層を薬局で取り込んでいる点や、リアルの場でコミュニケーションを重ねることによる信頼感の積み上げは、薬局ならではの大きな強みだろう。局内で販売する健康商品と組み合わせた健康アドバイスや、各種測定器で自分の健康状態を把握する機会を提供できる点も、効率重視のAmazonファーマシーとの差別化ポイントだ。
一方で同氏はAmazonファーマシーの利便性も高く評価しており、「確かにとても便利」。局内にいる他の患者に自分の病気や相談内容を聞かれたくない人や、薬剤師の丁寧な説明よりも処方薬のスピーディーな受け取りを求める人、重大な病気や副作用などの心配がない元気な人や若い人などにとっては、薬局よりもAmazonファーマシーの方が相性は良い、と太鼓判を押す。
今後は、利便性やスピードを求める”Amazonファーマシー派”と、薬剤師との丁寧なコミュニケーションや健康相談を重視したい、あるいはオンラインでの購入に抵抗や不安がある”相談薬局派”の二極化が進みそうだ。その時々の状況やライフステージの変化で、両方をうまく使いこなす層も出てくるだろう。まだまだ従来の薬局の存在感は大きい。とは言え、電子処方箋が普及すればAmazonファーマシーに今後客が徐々に流れていくことは不可避。それを前提とした努力が薬局には求められるが、そもそも薬局を「健康相談ができる場所」と認識している患者が少ない、という壁が立ちはだかる。そこで、イベントに参加した本メディアの記者が質問してみた。
「かかりつけ薬局としての存在感を地域で強めていくには、『局内でどんな健康支援をするか?』といった視点だけでなく、『薬局は健康相談ができる場所だ』ということを認知する人の数をどう増やすか?』という視点も必要だと感じている。認知を上げていく取り組みとしては、どんなことが必要だと思うか?」
これについて同氏は、「健康度相談ができる薬局だ、ということをしっかりアピールする努力と継続的な活動が必要」。店内でポスターを掲示したり、局の入り口でのぼりを立てるといった視覚的なアピールはもちろんのこと、「ふらっと立ち寄れる」という気軽感も合わせてアピールし、地域住民の心理的ハードルを下げることも重要とのこと。また、Amazonファーマシーなどのオンラインサービスとかかりつけ薬局でできることの違いをわかりやすく明示することや、属性ごとに適した支援策を用意しておくことも、薬局での健康相談に関心を持ってもらうための一案だという。
イベント後半では、参加した薬剤師らが、利便性やスピードを好む若年層に向けた「かかりつけ薬局」としてのポジションの取り方や、健康相談の予約の必要性の有無、80〜90代の高齢女性の支援などについて質問が挙がった。最後に同氏は薬局の強みとして、「地域に根ざしていること、信頼関係を築きやすいこと、患者やその家族の健康状態や体を経時的に見れること、しっかりコミュニケーションが取れること」を挙げて締め括った。
Amazonファーマシーは、遅かれ早かれ今後広く普及していくと思われるが、当面は、年齢・地域・属性によっては、薬局派を貫く人たちがまだまだ大多数だろう。ただし、その中でも生き残る事ができるのは、的確な健康支援の実施と地域住民への継続的なPRで認知を高めた薬局に限られると予想される。今後どんな薬局の取り組み事例が登場するか、本イベントを通じて引き続きキャッチアップしていきたい。
運営元
本メディアを運営するウーマンズは、「産学官の女性ヘルスケアソリューションが、広く流通する社会」をビジョンに掲げ、女性ヘルスケア領域でビジネスを行う事業者の成長・イノベーション・マッチングを支援しています。女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーとして、業界ニュースの配信、市場分析、レポート発行、カンファレンスを開催。最新レポートや新着セミナーのご案内、ヘルスケア業界の重要ニュースなどは、ニュースレターで配信中。ぜひご登録ください!

「女性ヘルスケア」をテーマに、ビジネスカンファレンスの企画開催/BtoB展示会の企画開催/BtoCイベントの企画開催/業界人限定の交流会などを実施。多様な形で、企業動向や生活者動向に関する情報を集め、分析し、整理して、業界の皆さまに最新の知見をご提供しております
【編集部おすすめ記事】
■調剤薬局業界で活発化、進む6タイプの事業展開
■調剤薬局・医療施設・介護施設への販路開拓を徹底解説 ~業界商習慣・規制・営業戦略~
■オンライン服薬指導の“リアルな限界”とは? 消費者ニーズに応える薬局の新しい形
■京セラ×マイライフ、世界初の「エクオールを薬局で即時検査」 実証実験開始
■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策
■女性の健康意識・健康行動・ヘルスリテラシーがわかる調査記事、33選